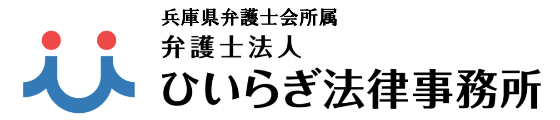労基署がチェックする就業規則のポイントをご存じですか?【経営者向け】

最終更新日 2024年8月28日
 今回も、前回に引き続き、就業規則の第2弾です。
今回も、前回に引き続き、就業規則の第2弾です。
というのも、最近目にしたケースで、労働基準監督署(労基署)の調査が入り、就業規則について事細かく是正を求められた会社がありました。
そこで、今回は、就業規則について、前回よりも詳細に、労基署の労働基準監督官がチェックするポイントを中心にお伝えしますので、御社が大丈夫かチェックしてみてください。
それでは、順次質問していきます。
Q1 そもそも就業規則を作成していますか?
 前回と重複するかもしれませんが、そもそも、従業員10人以上の事業場は就業規則を作成し労基署長に届け出なければなりません。
前回と重複するかもしれませんが、そもそも、従業員10人以上の事業場は就業規則を作成し労基署長に届け出なければなりません。
ここで注意すべきことは、「事業場ごと」であって、「会社ごと」ではないという点です。
最近目にしたケースでは、会社の本社には就業規則がありましたが、本社と離れた工場には就業規則がありませんでした。
なお、ひな形を流用した就業規則であっても、労基署との兼ね合いでは、とりあえず作成し届け出ていれば、あまり文句を言われません。
ただ、ひな形を流用した就業規則は、後日労働者とトラブルになりやすいので、お勧めしないことは、前回お伝えしたとおりです。
Q2 すべての労働者について作成されていますか?
就業規則は、パートさんなどを含め、すべての労働者について作成することが必要です。
ちなみに、職種ごとに異なる就業規則を作成するのは構いません。
最近目にしたケースでは、ある専門施設で、特定の専門職の方に関する就業規則がすっぽり抜け落ちていたという例がありました。
こうしたケースは意外に多いので、注意が必要です。
Q3 就業規則の中で給与、退職金等について「別規則で定める」としている場合、ちゃんと別規則を定めていますか?
 就業規則には、必ず記載しなければならない事項があり、これを必要的記載事項といいます。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項があり、これを必要的記載事項といいます。
必要的記載事項について、別規則で定めるとしながら、実際は別規則を定めていない場合は、労基法違反となります。
ただ、そうした会社は結構多いようです。
Q4 就業規則を作成する際、適切に選任された従業員の過半数代表に意見聴取していますか?
就業規則を作成する際、従業員の過半数代表の意見を聴取し、届出の際、その意見を添付する必要があります。
ところが、たいていの会社は、社長の息のかかった従業員を指名して署名押印させているようです。
これは労基法違反ですし、就業規則の効力にも影響しかねません。
Q5 就業規則を労基署に届け出ていますか?
常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成するだけでなく、労基署長に届け出なければならないとされています。
もちろん、作成したら、届け出ていますよね?
Q6 就業規則を労働者に周知していますか?
就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示したり、備え付けたりして、労働者に周知しなければなりません。
ところが、最近目にしたケースで、就業規則を社長しか取り出せないロッカーに入れていたというのがあります。
就業規則を周知していなければ、労基法違反となるばかりか、就業規則が労働契約の内容にならず、後日労働者との紛争の際、とても困ることになります。
Q7 就業規則の規定内容に法令違反はありませんか?
当たり前ですが、就業規則が法令や労働協約に違反してはならないとされています。
また、違反する場合、その違反する部分について、就業規則が持つさまざまな効力が認められません。
ただ、自社の就業規則が数ある法令に違反するかどうかについて、経営者がチェックするのは困難なのが実情です。
この点、業界のひな形などを流用すれば、そうした問題が起こりにくいわけです。
ただ、ひな形を流用することのデメリットが大きいことは、すでにお伝えしたとおりです。
Q8 必要に応じ就業規則を変更し、届け出ていますか?
 就業規則は、いったん定めれば大丈夫というものではありません。
就業規則は、いったん定めれば大丈夫というものではありません。
法改正や会社の実情に合うよう、随時変更し、届け出る必要があります。
ところが、最近では、定年後再雇用やストレスチェックに関する最近の法改正に未対応の企業が多いようです。
いかがでしたか?
上記8つのQに対し、1つでもノーがある場合は、労災や労働者の通報をきっかけとして労基署調査を受けやすいといえます。
また、実際に労基署調査が入った場合、是正を求められたり、場合によっては刑事処分に向け書類送検!されかねません。
ところが、法制度やビジネス環境の変化が目まぐるしい今日、本業で忙しい経営者の皆さんが、就業規則の整備やメンテナンスを随時ちゃんと行っていくのは極めて困難といえます。
実際、当事務所が地元の大手企業の顧問に就任して就業規則をチェックしたところ、法改正に対応できていない不備が多数見つかり、ひやりとしたこともあります。
就業規則に不安のある経営者の皆さんは、できる限り労務に強い弁護士を顧問に付け、就業規則のメンテナンスを始めることをお勧めします。